【2025年版】eSIMと物理SIMの違い|メリット・デメリットと対応機種まとめ
スマホを契約するときに必ず必要になるのが「SIMカード」。近年は従来のプラスチック製カードを使う物理SIMに加え、端末に内蔵されたデータを書き換えて利用するeSIMが急速に普及しています。
「どっちを選ぶべき?」「eSIMって本当に便利なの?」と迷う方のために、この記事ではeSIMと物理SIMの違い、各メリット・デメリット、料金や対応機種を分かりやすく解説します。2025年の最新情報を反映しているので、これからスマホを購入・契約する方はぜひ参考にしてください。
eSIMと物理SIMの基本的な違い
物理SIMとは?
物理SIMは、従来から使われている小さなICチップ入りカードです。スマホ側のスロットに差し込んで使います。サイズはnanoSIMが主流で、多くのスマホに対応しています。
eSIMとは?
eSIMは「embedded SIM(組み込み型SIM)」の略称で、端末本体にチップが内蔵されています。契約情報をオンラインで書き換えて利用できるため、カードの抜き差しが不要です。キャリアや格安SIMのサイトから発行されるQRコードを読み取ることで、即時に開通できます。
eSIMのメリット
- 即日開通が可能:店舗に行かなくても、自宅でオンライン手続きだけで利用開始できる。
- カードの紛失・破損がない:物理的に存在しないため、失くす心配がない。
- 複数回線を1台にまとめられる:1台で複数のeSIMを登録可能。キャリアと格安SIMの併用も簡単。
- 海外旅行時に便利:現地の通信事業者が提供するeSIMを追加すれば、現地SIMを買う手間が不要。
- 環境負荷が少ない:カード製造・物流が不要でエコ。
eSIMのデメリット
- 対応端末が限られる:最新iPhoneやPixel、Galaxyなどハイエンド中心。古い機種は非対応。
- 移行がやや面倒:機種変更時は新端末に再発行手続きが必要。
- トラブル時の切り分けが難しい:SIMカードを差し替えて検証できないため、原因特定に時間がかかることも。
- 対応していない格安SIMもある:大手はほぼ対応済みだが、一部小規模MVNOは未対応。
物理SIMのメリット
- 幅広い端末で利用可能:古いスマホや海外端末も含め、ほぼ全ての機種に対応。
- 移行が簡単:カードを抜き差しするだけで機種変更が可能。
- トラブル切り分けが容易:別の端末に差せばSIMや端末の不具合を判断できる。
- 一部特殊サービスに対応:法人契約やM2M機器など、物理SIMでしか対応していないケースもある。
物理SIMのデメリット
- 紛失や破損のリスク:小さく薄いため取り扱いに注意が必要。
- 店舗での手続きが必要な場合が多い:再発行や契約変更はショップでの作業になることも。
- 回線の切り替えに時間がかかる:eSIMのように即日・オンライン完結が難しい。
料金面の違いはある?
基本的には、eSIMと物理SIMで料金差はありません。同じプランであれば月額料金は同一です。ただし、一部の格安SIMでは「eSIM限定プラン」を提供しており、こちらは物理SIMより数百円安い場合があります。
例:
- IIJmio:eSIM専用プランが月額440円から利用可能(データ通信専用)
- 楽天モバイル:物理SIM・eSIMどちらでも料金は同じ
対応機種一覧(2025年時点)
2025年現在、eSIMに対応している主な端末は以下の通りです。
iPhoneシリーズ
- iPhone XS以降の全モデル(SE第2世代・第3世代含む)
- iPhone 14以降(米国版)はeSIM専用
- 最新のiPhone 16/16e/17シリーズは国内モデルもeSIM対応
Androidシリーズ
- Google Pixel 4以降
- Galaxy S20以降の一部モデル
- Xperia 1 IV以降の一部モデル
- OPPO・HUAWEIなど一部SIMフリー機種
※ただし、キャリア版/SIMフリー版によってeSIMの有無が異なる場合があるので注意が必要です。
どちらを選ぶべき?利用シーン別のおすすめ
eSIMがおすすめな人
- オンラインで契約・開通をスムーズに済ませたい人
- 海外旅行や出張が多い人(現地eSIMを追加して使える)
- 複数回線を1台にまとめたい人(キャリア+格安SIM併用)
- 最新のiPhoneやPixelを使っている人
物理SIMがおすすめな人
- 古い端末や格安機種を使っている人
- 頻繁に端末を入れ替える人(差し替えが楽)
- 法人契約や特殊なIoT機器で利用する人
- eSIM非対応の格安SIMを利用したい人
まとめ:eSIMと物理SIMは「使い方」で選ぶのが正解
eSIMと物理SIMにはそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが絶対に優れているということはありません。
便利さ・柔軟さを重視するならeSIM、対応機種の幅広さ・トラブル対応のしやすさを重視するなら物理SIMが向いています。
2025年以降はeSIM対応端末がますます増え、キャリアや格安SIMのeSIM対応も標準になりつつあります。今後スマホを新しく購入するなら、eSIM対応機種を選んでおくと安心です。
関連記事
※本記事の内容は2025年時点の情報です。最新の料金・提供状況は公式サイトをご確認ください。


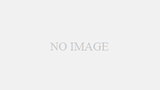
コメント